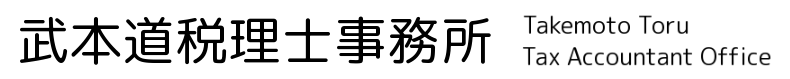交通費の実費請求は消費税の課税対象となるのか?
例えばコンサルタントの人など、顧問先に毎月のコンサル料を請求するときに、
・〇月分コンサル料 X,XXX円
・〇月分交通費 X,XXX円
という感じで交通費と本来の報酬を分けて請求書を作成する、ということも珍しくないと思います。
このとき、交通費の消費税区分は「課税売上」にしなければならないのでしょうか?
一つのアイディアとしては、支払ったときに「立替金」、請求・入金のときも「立替金」という通過勘定を使うことで、消費税区分は「対象外(不課税売上)」とすることもできそうな感じもしますが…
もしそうできるのであれば、簡易課税の人やインボイス制度2割特例適用の人にとっては有利です。これらの人は課税売上高に連動して納税額が増えるので、課税対象外にできれば納税額が減ります。
あと、基準期間の納税義務の判定(1,000万円)、簡易課税の適否の判定(5,000万円)という点でも、なるべく課税売上高にはしたくないケースは多いと思います。
ということで、今回の記事ではこの「実費請求」の問題について考えたいと思います。
国税庁の質疑応答事例「実費弁償金の課税」によると…
このような交通費の実費請求の問題に関して、国税庁は質疑応答事例(消費税)を公開しています。
-
弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費又は交通費が含まれていますが、これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか。
-
弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。
したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。
なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません。(消費税法基本通達10-1-4)
依頼者が『直接』交通機関に支払っている場合じゃないとダメと言っているわけですね。
これは以前の記事「講師の交通費は源泉徴収対象?」で書いた、『交通費も含めて源泉徴収対象となるのか否か』と同じ論点なのでしょう。
単なる経費の立て替えも課税売上になってしまうのか?
交通費は置いといて、それでは自社の事業とは全く関係ないような経費の立て替えも課税売上としなければならないのでしょうか?
そういった事例に対しても、国税庁はいくつかQAとして見解を示しているものがあるので紹介します。
国税庁の質疑応答事例「ホテルの客のタクシー代の立替払」によると…
以下のような質疑応答事例(消費税)があります。
-
ホテルにおいて客のタクシー代や宴会のコンパニオン派遣料等を立替払した場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
-
ホテル等が客の依頼を受けて、又は客が自らタクシーや宴会のコンパニオンを呼んだ場合においては、本来それらの役務の提供の対価は客が直接役務の提供者に支払うべきものですから、ホテルが当該対価を客に代わって立替払をし、その旨を明確に区分している場合には、その代金を客から領収しても課税の対象とはなりません。また、その支払はホテルの課税仕入れにも該当しません。
なお、タクシー代やコンパニオン代の実費にホテル等のマージンを上乗せして客から領収する場合には、単なる立替えとは異なりますので、その全額が課税の対象となります。
課税売上にはならないし、逆に支払うときも課税仕入れには該当しない旨が明記されていますね。
交通費のケースと異なるのは、『誰が負担すべきなのか』という点が明確なところでしょう。
ホテル会社は、客が勝手に手配したものを『間に入ってお金を受け渡ししているだけの存在』という立ち位置がハッキリしています。
なお、この質疑応答事例の【関係法令通達】の箇所には「消費税法第2条第1項第8号」と記載されており、その内容は消費税法の用語「資産の譲渡等」の定義についての記載です。
つまり、このタクシー代の受け取りは「そもそも【資産の譲渡等】に該当しない」という論理であると思われます。
国税庁の質疑応答事例「嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い」によると…
以下のような質疑応答事例(消費税)があります。
-
司法書士は、嘱託者の便宜等を考慮して、嘱託者が納付すべき登録免許税、登記手数料等を納付するために必要な印紙、証紙をあらかじめ購入しておき、嘱託を受けた事務に関してこれらの税、手数料等を納付する必要が生じた場合には手持ちの印紙等を貼付して手続きを行い、報酬を受領する際と区分して領収することとしています。
この場合、印紙等の購入時には不特定の者に対する仮払金(又は立替金)として処理し、使用金額を嘱託者から受領した時には、仮払金(又は立替金)の減少として処理しているときは、嘱託者から受領するこれらの代金は、司法書士の報酬(課税売上げ)に含まれないと考えてよいでしょうか。 -
法令上、嘱託者が納付すべきこととされている税、手数料等の立替払をし、その立替金を嘱託者から受領する場合において、質問のような方法により相手方にこれらの税、手数料等の立替金であることを明らかに区分して請求し、受領しているときは、司法書士の報酬に含まれないものとして、不課税とすることができます。(消費税法基本通達10-1-4)
この質疑応答事例でも参照されているのは、以下の消費税法基本通達です。
(消費税法基本通達10-1-4 印紙税等に充てられるため受け取る金銭等)
事業者が課税資産の譲渡等に関連して受け取る金銭等のうち、当該事業者が国又は地方公共団体に対して本来納付すべきものとされている印紙税、手数料等に相当する金額が含まれている場合であっても、当該印紙税、手数料等に相当する金額は、当該課税資産の譲渡等の金額から控除することはできないのであるから留意する。
(注)課税資産の譲渡等を受ける者が本来納付すべきものとされている登録免許税、自動車重量税、自動車取得税及び手数料等(以下10-1-4において「登録免許税等」という。)について登録免許税等として受け取ったことが明らかな場合は、課税資産の譲渡等の金額に含まれないのであるから留意する。
パッと見で分かりづらい文章ですが、要は「税金や公共手数料関係も基本は課税売上に含まれるが、顧客が本来納付すべき登録免許税や自動車税などは当該分として明記してれば課税対象外でOK」ということです。
なお、この質疑応答事例のQuestionでは「仮払金(または立替金)として処理する」という具体的な会計処理にまで踏み込んで説明されていますが、Answerでは「仮払金(または立替金)として処理してるとのことであれば…」という書きっぷりにはなっていません。
その理由は、上記の通り『通達に会計処理にまで踏み込んだ記載がない』ため、質疑応答のAnswerでもそこまでを要求できないのだと思われます。
国税庁の質疑応答事例「テナントから領収するビルの共益費」によると…
以下のような質疑応答事例(消費税)があります。
-
ビル管理会社等がテナントから受け入れる水道光熱費等の共益費等は、いわゆる「通過勘定」という実費精算的な性格を有することから、課税の対象外としてよいでしょうか。
-
ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。
また、水道光熱費等の費用がメーター等によりもともと各テナントごとに区分されており、かつ、ビル管理会社等がテナント等から集金した金銭を預り金として処理し、ビル管理会社等は本来テナント等が支払うべき金銭を預かって電力会社等に支払うにすぎないと認められる場合には、当該預り金はビル管理会社等の課税売上げには該当しません。
Answerの上段では、ビル管理会社が、例えば「水道光熱費(X月分)5,000円」のような請求の仕方をしている場合は、課税対象になると記載されていますね。このようなやり方だと利益が出る可能性もあるわけで、まぁ当然のことでしょう。
ちょっと特殊なことを書いているのがAnswerの下段で、ここでは「預り金として処理」という会計処理にまで踏み込んで条件を付けています。司法書士の質疑応答とは少し違いますね。
消費税法基本通達10-1-16「別途収受する配送料等」
以下のような消費税法基本通達があります。
(消費税法基本通達10-1-16 別途収受する配送料等)
事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。
ここでも「預り金又は借受金等として処理」という会計処理にまで踏み込んで条件を付けていますね。
さて、会計処理にまで踏み込んで記載するケースと、そうでないケースがそれぞれ存在するのは一体なぜでしょうか?
これはおそらく、例えば司法書士が依頼者の登録免許税を代行納付するケースは、『本来負担すべきは依頼者』ということが誰が見ても明らかだからかなと思います。税理士が納税者の税金を代行納付することも稀にありますが、それも同様でしょう。納付書を見れば、誰が納税義務者かは書いてあります。
こういうケースでは、会計処理にケチをつけるまでもない、という感じでしょうか。
一方で、管理会社の水道光熱費や、小売店の配送料などは、実費ではなく一定額として請求して、その部分からも利益を狙うというケースは少なくないです。
そういったケースでは、「立替金として処理したいのであれば【この部分は売上とは別物である】ということを明確に意思表示してくださいね」という意味合いで、国税庁は会計処理にまで踏み込んだ要求をしているのではないか、と個人的には思います。
まとめ
上記の質疑応答事例や通達などを整理すると、立替分を消費税の課税対象外として請求するためには、大前提として以下の要件があることになります。
- 実費を請求し、請求書でも明らかに区分すること
そして、「本来負担すべきは他者である」と言えるかどうか、その強弱によって、必要条件も以下の表のように変わってくるのかなと思います。(私見です。)
| 「本来負担すべきは他者」であることが… | 必要条件 |
|---|---|
| 明らか(税金等) | 「課税対象外」でOK(ただし預り金等で処理した方が望ましい) |
| 微妙(水道光熱費、配送料等) | 預り金等で処理することを条件に「課税対象外」でOK |
| 微妙(交通費) | 「課税対象外」はNG |
「本来負担すべきは他者」であることが明らかな税金等の場合でも、やはりなるべくは預り金等で会計処理するのが望ましいのは間違いないでしょう。
つぎに、「本来負担すべきは他者」であることが水道光熱費、配送料等の場合は、預り金等で会計処理することを条件に、「課税対象外」とすることが認められるのかな、と。
※「預り金等で会計処理」というのが、「預り金」以外に具体的に何の勘定科目だったらOKで何だったらNGというのは明記されていないので何とも言えないのですが、少なくとも「売上高」で処理するのはNGでしょう。(通達等の「預り金等として処理」という文言には「売上高とは分けて」という意味合いが含まれると思うため。)
そして交通費の場合は、会計処理に関わらず「課税対象外」とすることはできないのだと思います。
以上、個人的に色々と考えてきたことを、思考整理も兼ねて記事にしました。私見も多いので、正確性を保証できるものではないことはご了承ください。
スマホで固定電話なら【03plus】解説記事は
こちらのリンク先からどうぞ。
紹介ID「0926004794」でAmazonギフト券2,000円!
0円スタートプラン
![]() で気軽に開始可能。
で気軽に開始可能。
法務局に行かずに変更登記申請 —【GVA法人登記】公式クーポンコードで1,000円OFF!解説記事はこちらのリンク先からどうぞ。
無料から使えるクラウド会計ソフトなら【freee会計】最大3,576円OFFのクーポンコードにご興味の方は こちらのリンク先からどうぞ。