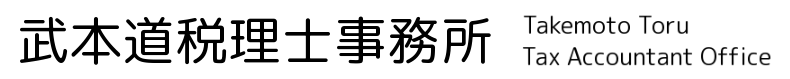調整対象固定資産と高額特定資産の違いは?(比較して整理)
消費税の不当な還付を狙ったスキームを防ぐために、消費税法には「調整対象固定資産」と「高額特定資産」を取得した際の制限措置が設けられています。
この2つは似たような概念ですが、違うところも多く調べ直すことも多いので、自分自身の知識の整理の意味も含めて記事にして解説したいと思います。
対象資産
調整対象固定資産と高額特定資産のどちらも、「建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産」がその対象となりますが、それが棚卸資産の場合は「調整対象固定資産」になることはありません。
例えば不動産再販業者の建物、中古車販売業の車などは棚卸資産になるので、高額特定資産にはなり得ますが、調整対象固定資産とはなり得ません。
これらの種類の資産であり、かつ一の取引の単位※が「税抜対価100万円以上」の場合は調整対象固定資産に該当し、「税抜対価1,000万円以上」の場合は高額特定資産に該当することになります。
「一の取引の単位※」については、これはこれで論点が多くなるので、別の記事で解説予定しております。
⇒「一の取引の単位」とは?(調整対象固定資産/高額特定資産)
制限措置の発動条件
調整対象固定資産の取得
- 資本金1,000万円以上の法人の設立2期以内
- 特定新規設立法人の設立2期以内
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した年度を含めて2年間
上記いずれかに該当する期間で原則課税(≠簡易課税)を適用中に、「調整対象固定資産」を取得したときに制限措置が発動します。
高額特定資産の取得
消費税の納税義務者(≠免税事業者)で原則課税(≠簡易課税)を適用中に、「高額特定資産」を取得したときに制限措置が発動します。
2024年度税制改正により、「その課税期間において金又は白金の地金等の額の合計額200万円以上である場合」も高額特定資産の取得があったときの制限措置の対象に加わりました。(2024/4/1から適用開始。)
制限措置の内容
調整対象固定資産または高額特定資産を取得した年度を含めて3年間、事業者免税点制度の適用が不可能となります。さらに「原則課税で申告したくないから簡易課税制度を選択する」といったことも制限されます。(原則課税が強制されます。)
仕入税額控除の調整
制限措置とはちょっと視点が異なるところですが、調整対象固定資産の取得して仕入税額控除を受けていた場合で、取得の翌々年度に課税売上割合の著しい低下など一定の理由があったときには、仕入税額控除の金額の調整が必要となる場合があります。
※高額特定資産には該当するが調整対象固定資産には該当しない場合、つまり棚卸資産の場合には、この調整計算の対象とはなりません。
まとめ
似たような概念でも違いは多くあることがわかりました。
ちなみに、「調整対象固定資産/高額特定資産の制限措置に該当したかも?」とヒヤリとはしても、そもそも発動条件を満たしていなかったり、発動していても悪影響が無かったりするケースが、実務上は大半かなという印象ではあります。
そもそもは「自販機スキーム」と言われる不動産投資の不当な消費税還付を防ぐことが、これらのルールの発端ですからね。
通常の事業を行っている人にとってはあまり気にしなくても良いかもしれませんが、もしかしたら知らぬうちに制限措置が発動しているケースもあり、その場合は被害甚大なので、注意しておくことに越したことはないでしょう。
スマホで固定電話なら【03plus】解説記事は
こちらのリンク先からどうぞ。
紹介ID「0926004794」でAmazonギフト券2,000円!
0円スタートプラン
![]() で気軽に開始可能。
で気軽に開始可能。
法務局に行かずに変更登記申請 —【GVA法人登記】公式クーポンコードで1,000円OFF!解説記事はこちらのリンク先からどうぞ。
無料から使えるクラウド会計ソフトなら【freee会計】最大3,576円OFFのクーポンコードにご興味の方は こちらのリンク先からどうぞ。